相続

ご家族やご親族が亡くなられると、相続手続きを行う必要があります。
相続手続きでは、相続人の調査・確定とともに、相続財産の調査・目録の作成を行い、必要に応じて遺産分割協議書を作る必要があります。
普段それほどお付き合いのないご親族や遠方にお住まいの方が相続人に含まれる場合には、相続手続きは非常に労力がかかります。
主な対応業務
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・目録作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄に関する書類作成支援
- 相続全般に関するサポート
遺言
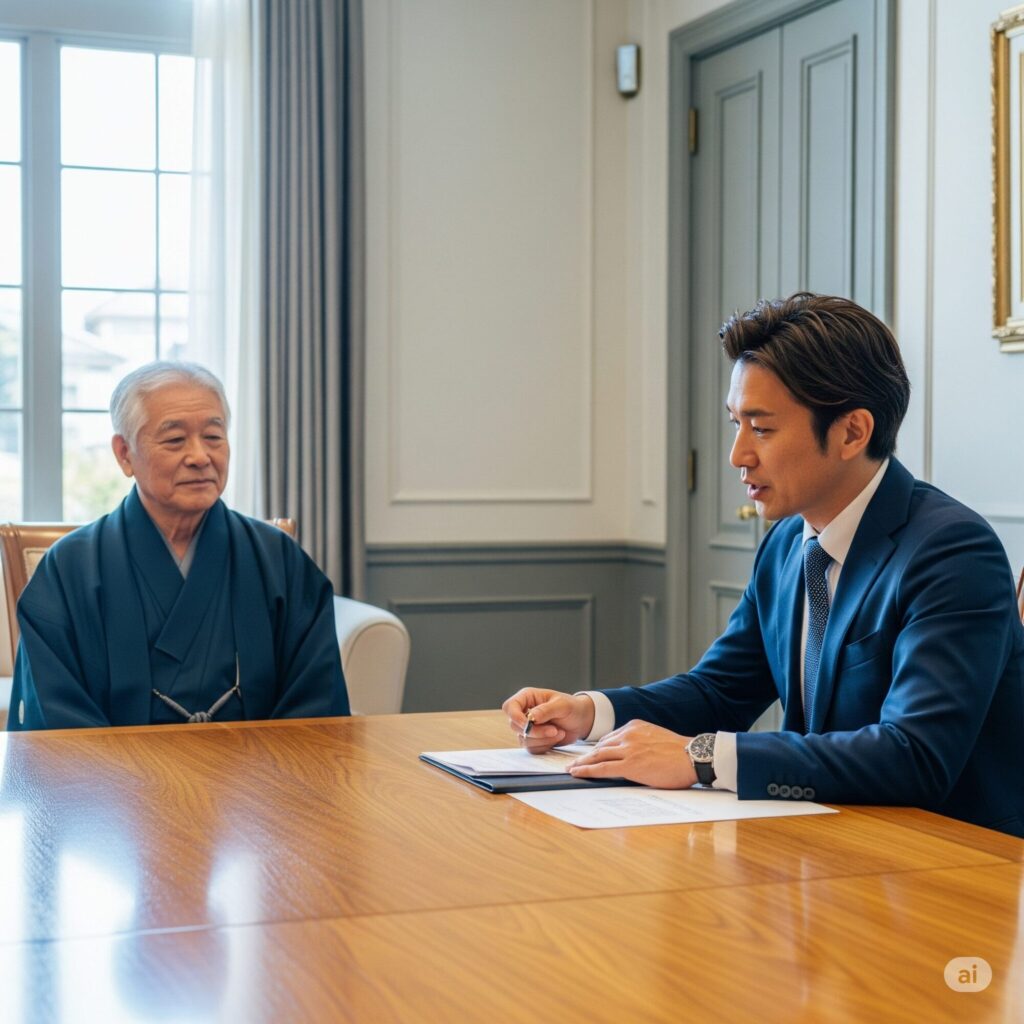
民法では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つが定められています。
- 自筆証書遺言:遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成する遺言です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると家庭裁判所での検認が不要となります。 - 公正証書遺言:公証役場で公証人が、証人2人以上の立会いのもと、遺言者の口述に基づいて作成する遺言です。
費用はかかりますが、最も信頼性が高いと言えます。 - 秘密証書遺言:遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、封印し、その封印された遺言書を公証人と証人2人以上に提出して、自分の遺言書である旨を申述する形式の遺言です。
遺言書の内容を秘密にしたい場合に有効ですが、遺言書自体の内容に不備があると、遺言が無効となる恐れがあります。
せっかく遺言を作成しても、不備があると無行となったり、内容によっては、相続人間でトラブルが起こることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
主な対応業務
- 自筆証書遺言の作成支援
- 公正証書遺言の作成支援
- 遺言作成全般に関するアドバイス
後見

後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分になった方を法的に保護し、支援するための制度です。
大きく分けて以下の2種類があります。
任意後見制度:将来、判断能力が低下することに備え、判断能力があるうちに、ご自身で信頼できる人(任意後見人)を選び、将来どのような支援を受けたいかを契約(公正証書)で決めておく制度です。実際に判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。
法定後見制度:既に判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人などを選任し、その方の財産管理や契約などの法律行為を支援しするものです。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
主な対応業務
- 任意後見契約の内容に関する相談・アドバイス
- 任意後見契約書の原案作成
- 財産目録の作成支援
- 任意後見監督人選任申立てのサポート
- 死後事務委任契約書の作成支援
家族信託

家族信託とは、ご自身の財産を、ご自身が信頼する家族に託し、その家族がご自身の目的に沿って財産を管理・運用・処分する仕組みです。
従来の成年後見制度や遺言では対応しきれない、柔軟な財産管理や承継を実現できる新しい財産管理・承継方法として注目されています。
主な対応業務
- 家族信託に関する相談・コンサルティング
- 信託契約書の原案作成(公正証書による作成を推奨)
- 信託財産に関する調査サポート
- 信託契約後のサポート
- 司法書士、税理士等の他士業との連携調整
